神武天皇、孔舎衛坂(くさえざか)で敗退し、五瀬尊が傷つく・・
孔舎衛坂(くさえざか)で敗退し、五瀬尊が傷つく
大台ケ原の牛石ヶ原(神武天皇の銅像あり) |大台ケ原から井光(いひか)を通って宮滝へ
大台ケ原の牛石ヶ原(神武天皇の銅像あり) | 和田 | 井光神社 | 井光神社の奥宮| 川上鹿塩神社 | 大蔵神社 | 岩神神社 | 宮滝 |
神武天皇、宇陀制圧の前編
宮滝 | 十二社神社 | 宇陀の高城 | 桜実神社| 宇賀神社 | 穿邑顕彰碑 | 三島神社 | 田口の血原橋 | 熊野神社 | 宮城(みやしろ) |
宮滝(宮瀧)から菟田の高城までで神武天皇に関わるかもしれない神社
吉野山口神社 ・ 高鉾神社 | 剣主神社 | 宮奥ダム神武天皇、宇陀制圧の後編
高城岳(たかぎだけ) | 城山(旧、高倉山) | 高角神社(現、高倉山) | 笑ヶ嶽 | 屑神社 | 皇大神社 | 音羽山 | 是室山| 伊奈佐山 | 神武の渕 | 御井神社 | 福地岳 | 墨坂伝承地 | 墨坂神社 |
高龗神社(たかおかみ) | 吉隠川(よなばりがわ) | 慈恩寺佐野 | 生根神社
朝原祈祷の5つの伝承地(南から)
丹生川上神社(中社) | 魚見岩(うおみいわ) | 神部神社(かんべ) | 八坂神社 | 阿紀神社 | 丹生神社白庭(生駒市周辺)で長髄彦の反乱軍の鎮圧
鵄邑(とびむら)顕彰碑 | 鵄山(とびやま)伝承地 | 長髄彦本拠地 | 鳥見白庭山| 饒速日命墳墓(日の窪山) | 「御炊屋姫の墓」という碑 |
哮ノ峯(磐船神社の北) | 磐船神社
| 「眞弓塚」という碑がある | 眞弓塚(かつての白庭山か?) | 伊弉諾神社(眞弓山の長弓寺にある) |
瓊々杵尊の兄・天之火之明尊が飛鳥治君に(第一次天孫降臨)
石切剱箭神社(いしきりつるぎや) | 石切神社(上の社)| 哮ノ峯(生駒山の北麓) | 日下山(饒速日山・草加山) | 生駒山 | 宝山寺 |
(※)参考ページ ⇒ 「神武天皇大和討ち」
神武天皇、生駒山直越〜『日本書紀』の記述から
「戊午春2月11日、吉備高島宮を出発した一行は、3月10日川をさかのぼって河内国草香邑の青雲の白肩津についた。」
この当時の大阪平野は大きな湖(河内湖)があり、その湖に北から淀川、南から大和川が流れ込んでいたようである。大和川は現在は南を流れているがこの当時は河内湖に流れ込んでいた。河内湖と海をつなぐ水路は大和川であった。
当時はこのあたりまで湖が広がっていたのである。
善根寺には現在春日神社があり、この神社から生駒山越えの道が通じており、その入り口に佐野命の孔舎坂(くえさか)古戦場石碑が建っている。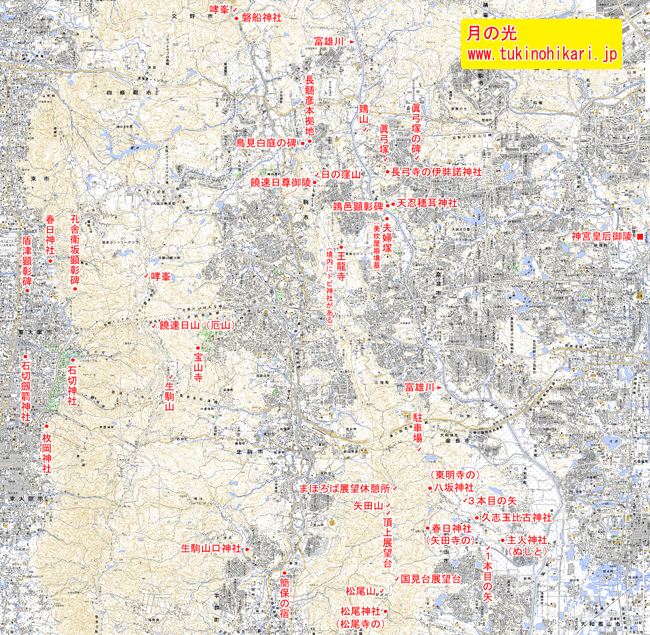
この当時の大阪平野は大きな湖(河内湖)があり、その湖に北から淀川、南から大和川が流れ込んでいたようである。大和川は現在は南を流れているがこの当時は河内湖に流れ込んでいた。河内湖と海をつなぐ水路は大和川であった。
日本書紀に「川をさかのぼって」とあるのは、大和川のことであろう。
「河内国草香邑の青雲の白肩津」というのは現在の善根寺の周辺といわれている。当時はこのあたりまで湖が広がっていたのである。
善根寺には現在春日神社があり、この神社から生駒山越えの道が通じており、その入り口に佐野命の孔舎坂(くえさか)古戦場石碑が建っている。
白肩津は現在の「盾津顕彰碑」のあるあたりだろう
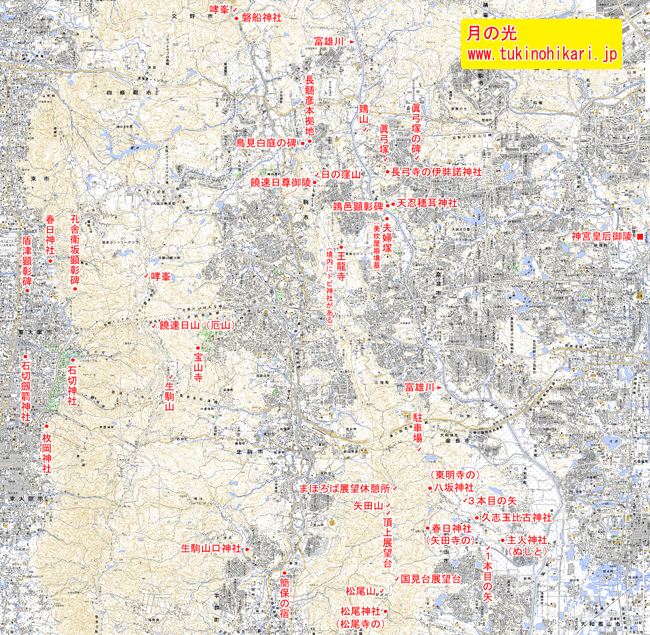
「河内国草香邑の青雲の白肩津」とは「盾津」のこと
http://www.geocities.jp/iko_kan2/kusakayama.html より
日下と書いてなぜ「クサカ」と読むのか?ということですが、その語源にはいろいろな説があります。
その中で、古くは「日の下(した・もと)のクサカ」という言い方があり、クサカの地が、山越え道を通じて大和の入口にあたる重要な地として一早く開かれ、この地クサカの背後に連なる生駒山から上る太陽つまり日下(ひのした)を「くさか」と訓むようになったという説が有力です。
古代の文献、『古事記』や『日本書紀』の神武天皇東征の物語に、皇軍が日向から筑紫〜吉備を経て大阪湾のさらに奥、生駒山のふもと日下の入江にあった「河内国草香邑青雲白肩之津」に上陸したことが書かれていて、大和への入口の地として初めて日下の地が登場します。
皇軍は、大和へ入るため、一度は南下して龍田に出ようとしましたが難行して再び引き返し、直ちに東へ向かって膽駒山(生駒山)を越えようとしましたが、これを知った長髄彦(ながすねひこ)は、孔舎衛坂(くさえざか)で激しく防戦したため、皇軍は戦利なく後退し、兄の五瀬命(いつせのみこと)も負傷された。
これは、東方の日(太陽)に向かって進んだための不吉である、として草香津へ引返し、盾を立て並べて雄叫びしたので、この津を「盾津」と改めた、という話はよく知られています。
皇紀二千六百年(昭和15年)の記念に向けて行われた神武天皇御東遷聖蹟調査にもとづいて、現在の孔舎衙小学校の東側に高さ3.3mの「 神武天皇聖蹟 盾津顕彰碑 」が大阪府によって建てられています。
日本書紀によると、3月10日に白肩津に着いた一行は、4月9日に龍田を越えて大和に入ろうとしたが、道が険しく断念して、生駒山直越え(ただこえ)の道を選んだとある。
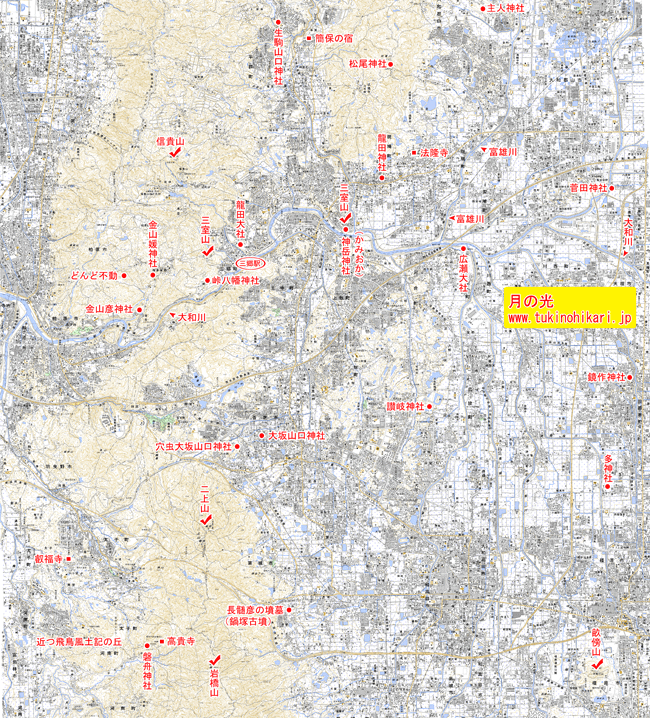
龍田越えとは、信貴山の南部から大和川の北側を龍田大社に抜ける街道のこと
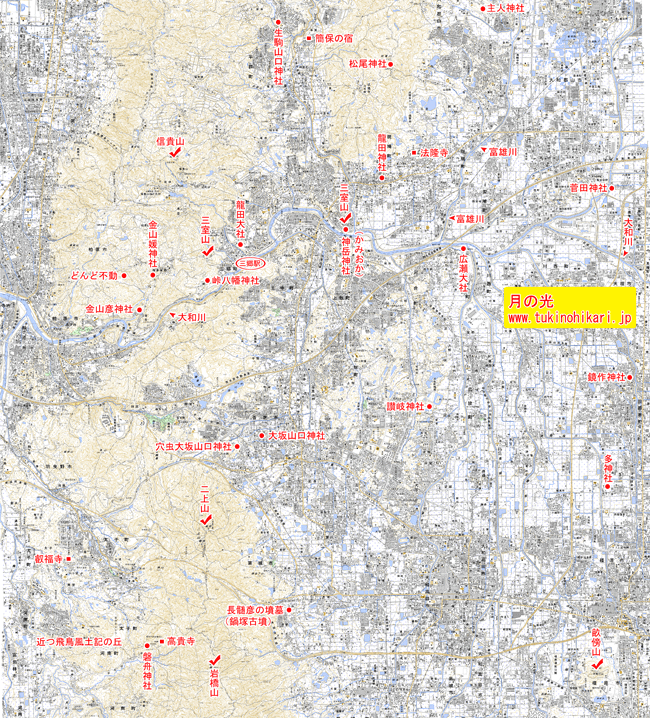
なぜ生駒山直越え(ただごえ)の道を選んだのだろうか? 〜 大和へ行く4つのルート
〔1〕大和川をさかのぼって大和にたどり着くのが、この当時のもっとも標準的な大和への道だった。〔2〕龍田越えは大和川にほぼ準じた山越えの道であり、古代から開かれていたようであるが、白肩津からはかなり南回りの道である。
〔3〕白肩津から少し北へ回れば、饒速日命が大和進入に使った天の川に沿った道が存在する。
〔4〕神武天皇が進まれた生駒山直越え(ただこえ)の道。
陸路を選ばれた理由は・・・
大和国内にいる長髄彦の反乱軍は、川船の動きを全て封鎖していた。そのため、天の川と大和川を利用できなかったのだ。
まずは、矢田丘陵にいる饒速日尊との直接交渉である。
矢田丘陵にいる饒速日尊のところに行くために、龍田山を越えて、富雄川を北上する道を選ばれたのだろう。
白肩津に到着してから龍田越えを実行するまでに日本書紀で1ヶ月かかっている。
この期間は大和やその周辺の情報集めに費やされた。
使者を周辺に派遣して、長髄彦の反乱軍の状況や、地理を把握し、それらの情報を元に大和への進入経路を検討したものであろう。
龍田越えを断念したのは、軍を通すには難所が多い上に、さらに長髄彦の反乱軍に龍田越えを察知されてしまったからだろう。
生駒山直越え(ただごえ)コース
大和に河内から進入する経路のすべてが長髄彦反乱軍によって封鎖されている。
長髄彦側はその動きを察知して、饒速日山に軍を配置して佐野命一行がやってくるのを待ち構えて矢を放って追い返したのである。
このとき兄五瀬命の肘脛(ひじはぎ)にあたった。
そこで、この山を「厄山」と呼ぶようになった。
生駒山直越えコースの山頂部は饒速日山と呼ばれており、饒速日尊が大阪方面を統治していた頃、河内と大和の両方に見晴らしが利くこの山に拠点を置いていたのだろう。
この当時はその祭祀施設が残っており、饒速日尊の聖地(饒速日尊の御殿址の伝承地あり)となっていた。
神武天皇の最大の目的は皇統を正し示すことにあった。
それには、矢田丘陵にいる饒速日尊との直接交渉が一番の近道である。長髄彦側はその動きを察知して、饒速日山に軍を配置して佐野命一行がやってくるのを待ち構えて矢を放って追い返したのである。
このとき兄五瀬命の肘脛(ひじはぎ)にあたった。
そこで、この山を「厄山」と呼ぶようになった。
生駒山直越えコースの山頂部は饒速日山と呼ばれており、饒速日尊が大阪方面を統治していた頃、河内と大和の両方に見晴らしが利くこの山に拠点を置いていたのだろう。
この当時はその祭祀施設が残っており、饒速日尊の聖地(饒速日尊の御殿址の伝承地あり)となっていた。
神武天皇、盾津へ退却
神武天皇は草香津に引き返し盾を並べて盾津と呼び、雄たけびを挙げて士気を鼓舞した。幸い敵が深追いして来なかったので武器、兵糧、兵員の撤収を完了し、四月二十三日に盾津から出発して再び大阪湾に船団を浮かべた。
【地図】生駒山・饒速日山・哮峯の詳細地図
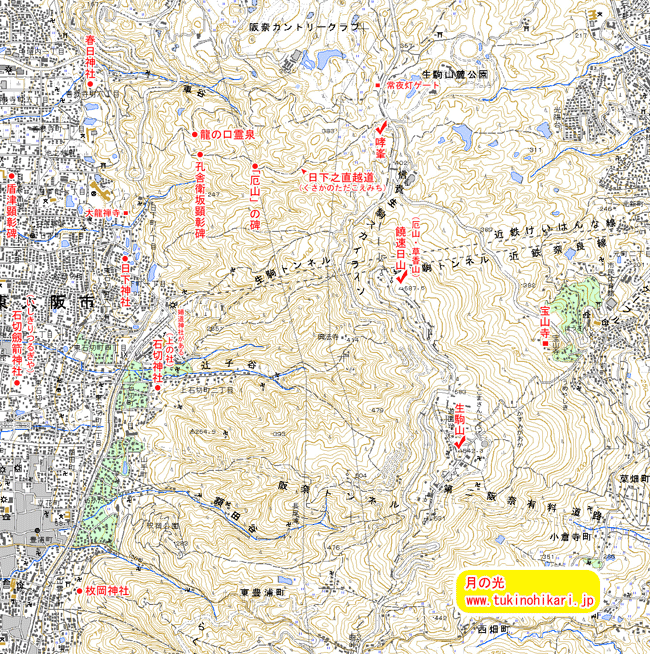
Copyright (C) 2002-2009 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.
お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。
