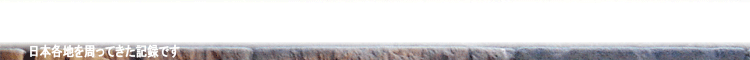平成21(2009)年5月30-31日、神武天皇「大和討ち」-
朝原祈祷から桜井市慈恩寺佐野の制圧まで
「神武天皇大和討ち」に基づいて参拝。
神の世から人の世への移り変わりの事柄を、一応、岩戸にかくして神ヤマトイワレ彦命として、人皇として立たれたのであるから、大きな岩戸しめの一つであるぞ。
『 新版 ひふみ神示』下巻 所収 五十黙示録第二巻碧玉之巻第十帖より
神武天皇の岩戸しめは、御自ら人皇を名乗り給ふより他に道なき迄の御働きをなされたからであるぞ。神の世から人の世への移り変わりの事柄を、一応、岩戸にかくして神ヤマトイワレ彦命として、人皇として立たれたのであるから、大きな岩戸しめの一つであるぞ。
記憶が想起されてくるようだ。
19箇所で祝詞奏上
平成21(2009)年5月30日(土曜日)、朝原祈祷
墨坂伝承地は、民家の塀に隣接してある。
日中に近辺をウロウロしていると不審者と間違われるのも嫌だったので、早朝の6:00に着いた。
神武天皇が伊那佐山を越え、福地岳を越えて、北側から墨坂の地を制圧したと伝わる。
神武天皇即位4年、霊畤(まつりのにわ)を鳥見山の中に立てて、その地を名付けて、上小野の榛原、下小野の榛原という。
鳥見山中霊畤(とみやまなかまつりのにわ)の「下小野の榛原」が墨坂伝承地である。
祟神天皇の時、この地から現在の墨坂神社の地に祀りかえられている。
「長い間あなた様をお待ち申し上げておりました」
こういう声が前日の出発前・木曜日からから聞こえていた。
山頂に直径60cm程の球形の石を神籬(ひもろぎ)とする、神日本磐余彦命、高龗神(たかおかみのかみ)を祀る小祠がある。
神武天皇滞在の聖蹟と伝えられている。
周辺の葛神社、十八社神社、椋下神社、天神神社、雨師丹生神社、八咫烏神社、高角神社、桜実神社、龍穴神社、八竜五社神社等、神武天皇関連人物を祭る神社は悉く高城岳を向いている。
高城岳から東の展望はあまり利かないが南から西への展望は良く利く、大和盆地が一望でき、晴れた日には大阪湾も見えるほどである。
饒速日尊が降臨された伝承が残っているらしい。
御井神社の鳥居横で農作業をされている方に「神武の淵」のことを聞いても知らないというし、「墨坂伝承地」近くのローソンの店員に聞いても知らなかったし、知っている人はいないのかも知れない。
神武天皇が伊那佐山を越え、福地岳を越えて、北側から墨坂の地を制圧したと伝わる。
神武天皇即位4年、霊畤(まつりのにわ)を鳥見山の中に立てて、その地を名付けて、上小野の榛原、下小野の榛原という。
鳥見山中霊畤(とみやまなかまつりのにわ)の「下小野の榛原」が墨坂伝承地である。
この地から祟神天皇の時、現在の墨坂神社の地に祀りかえられている。
前回行ったときなんという山か気になっていた。今回宮城(みやしろ)に行く前に血原橋バス停に立ち寄って、中のおばあさんに尋ねた。
「杉山岳だよ、右のほうに見えてくるのが三郎岳だよ」
高城岳はこの土地からはみえないという。
今回の行程で
「宮城(みやしろ)に行くように」
と言われていた。
山に入る人が道に迷わないように、林道の杉の幹に黄色のテープやら赤のテープを巻いて目印にしている。
宮城(みやしろ)と思われる平坦部についた。
ここには夢で何度か来たことがある思った。
最初に来たのは1997年のことだったと思う。
その後、夢では何度かやってきている。
私にとってとても大事なところらしい。
神武天皇が宮を築いたと伝えられる宮城(みやしろ)だ。
大宇陀区守道に高倉山と呼ばれている山がある。
この山の山頂部には高角神社のある高倉山が存在しており、「神武天皇聖蹟 菟田高倉山顕彰碑」が立てられており、日本書紀にいうところの高倉山であると伝えられている。
しかし、松山城址のある城山に伝わる伝承では、この山も高倉山といい、昔高倉神社が存在したそうであるが、この山に松山城を築城するとき高角神社のある高倉山に神社を遷したと伝えられている。
この伝承を基にすると、佐野命が国中を眺めた高倉山というのは現在松山城址のある城山といわれている山となる。
この山は天皇が見たような軍の配置を最も良く見ることのできる位置に存在しているので、大宇陀区の松山城址のある城山こそ真実の高倉山であろう。
ある女神、
「長い間お待ち申し上げておりました」
烏(からす)の一群が声を上げている。
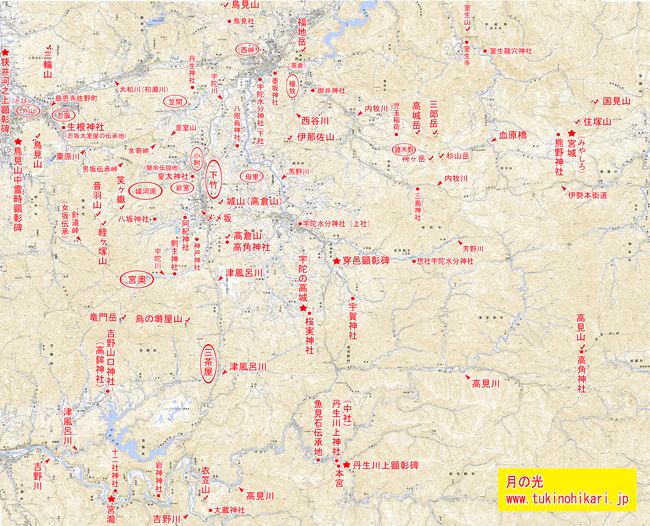
日中に近辺をウロウロしていると不審者と間違われるのも嫌だったので、早朝の6:00に着いた。
| 墨坂伝承地 | 奈良県宇陀市榛原区あかね台1丁目2-16 |
神武天皇即位4年、霊畤(まつりのにわ)を鳥見山の中に立てて、その地を名付けて、上小野の榛原、下小野の榛原という。
鳥見山中霊畤(とみやまなかまつりのにわ)の「下小野の榛原」が墨坂伝承地である。
祟神天皇の時、この地から現在の墨坂神社の地に祀りかえられている。
朝原祈祷の前に作戦を練った高城岳に向かった
| 児玉稲荷 | 奈良県宇陀市榛原区諸木野 |
こういう声が前日の出発前・木曜日からから聞こえていた。
児玉稲荷のご神前に立ち、そして高城岳に登った。
| 高城岳 | 奈良県宇陀市榛原区諸木野 |
神武天皇滞在の聖蹟と伝えられている。
周辺の葛神社、十八社神社、椋下神社、天神神社、雨師丹生神社、八咫烏神社、高角神社、桜実神社、龍穴神社、八竜五社神社等、神武天皇関連人物を祭る神社は悉く高城岳を向いている。
高城岳から東の展望はあまり利かないが南から西への展望は良く利く、大和盆地が一望でき、晴れた日には大阪湾も見えるほどである。
高城岳を下りて、御井神社、神武の渕、福地岳、墨坂神社を周った
|
御井神社 (饒速日尊降臨伝承地) |
奈良県宇陀市榛原区檜牧964 |
| 神武の淵 | 奈良県宇陀市榛原区檜牧 |
| 福地岳 | 奈良県宇陀市榛原区檜牧 |
| 墨坂神社 | 奈良県宇陀市榛原区萩原709 |
鳥見山中霊畤(とみやまなかまつりのにわ)の「下小野の榛原」が墨坂伝承地である。
この地から祟神天皇の時、現在の墨坂神社の地に祀りかえられている。
宮城(みやしろ)へ
| 血原橋から見えるのは杉山岳 |
「杉山岳だよ、右のほうに見えてくるのが三郎岳だよ」
高城岳はこの土地からはみえないという。
| 宮城(みやしろ) | 奈良県宇陀市室生区黒岩 |
「宮城(みやしろ)に行くように」
と言われていた。
山に入る人が道に迷わないように、林道の杉の幹に黄色のテープやら赤のテープを巻いて目印にしている。
宮城(みやしろ)と思われる平坦部についた。
ここには夢で何度か来たことがある思った。
最初に来たのは1997年のことだったと思う。
その後、夢では何度かやってきている。
私にとってとても大事なところらしい。
神武天皇が宮を築いたと伝えられる宮城(みやしろ)だ。
|
高角神社 (高倉山にある) |
奈良県宇陀市大宇陀区守道第776番 |
この山の山頂部には高角神社のある高倉山が存在しており、「神武天皇聖蹟 菟田高倉山顕彰碑」が立てられており、日本書紀にいうところの高倉山であると伝えられている。
しかし、松山城址のある城山に伝わる伝承では、この山も高倉山といい、昔高倉神社が存在したそうであるが、この山に松山城を築城するとき高角神社のある高倉山に神社を遷したと伝えられている。
この伝承を基にすると、佐野命が国中を眺めた高倉山というのは現在松山城址のある城山といわれている山となる。
この山は天皇が見たような軍の配置を最も良く見ることのできる位置に存在しているので、大宇陀区の松山城址のある城山こそ真実の高倉山であろう。
|
松山城址のある城山 (旧、高倉山か?) |
奈良県宇陀市大宇陀区春日 |
「長い間お待ち申し上げておりました」
烏(からす)の一群が声を上げている。
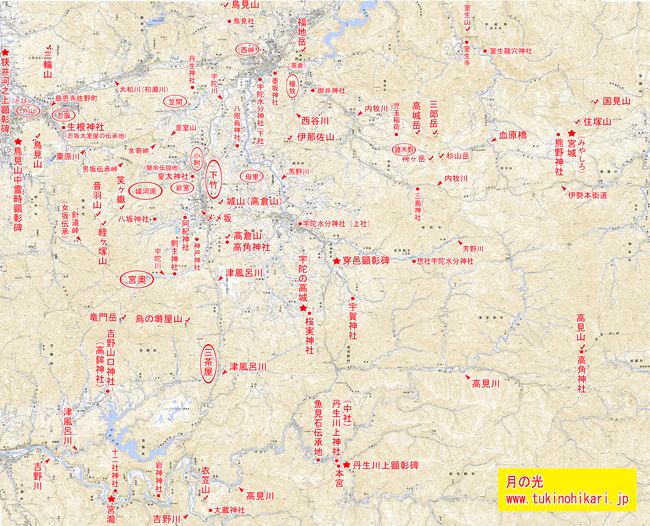
平成21(2009)年5月30日(土曜日)の宿泊は
かんぽの宿 奈良 奈良県奈良市二条町3-9-1 (0742-33-2351)平成21(2009)年5月31日(日曜日)、宇陀という地域は・・
かんぽの宿 奈良から車を走らせると、一匹のハエが飛び込んできた。
何度か追い出そうとしたのだが出てくれないため、ティッシュペーパーで捕まえて出すことになった。
丸めたティッシュでハエを掴んだ瞬間、ハエは次のように言った。
「わが身をあなた様に捧げます」
と。
ハエの王はベルゼブブとして象徴されている。
「好きにさせておくように」
いつもの声だ。
ベルゼブブが戻れる時が近いのかもしれないが、まだ先のことだ。
墨坂を制圧して神武天皇が初めて大和の地に立った場所である。
大室伝承地の一つ。
大室伝承地はここだろう。
この地で残党を一掃した後、女軍を配置して墨坂攻略の陣を張った。
女神が現れて、
「あなたさまをお慕い申し上げます」
そういう声だ。
神武天皇の名前の由来になった神社である。
「ここに来ないとかむやまといわれひこのみことにはなれないんだよ」
この言い方はいつもの声だ。
今日がお祭りのようだった。
お祭りの準備をしているおじいさんとおばあさんに音羽山が見えるかどうか聞いた。
実に詳しいおじいさんが出てこられた。
阿紀神社から音羽山は見えないが、本郷川を隔てたスグ向こうの「かぎろひの丘」に上がれば音羽山が見えること、西山岳の上を空山といい、空山から一段低くなったところを西山岳というのだそうだ。
「メメ坂」という地名も使っていたし、実に詳しい方だと思った。
八坂神社から音羽山が見えるかどうかも尋ねると、八坂神社からでは音羽山は近すぎて見えないという。
祝詞奏上後、レッドリバー犬を連れた女の子がやってきて、自分が作った小さい弓で矢を射て遊んでいる。
今の子が弓と矢を自分で作って遊ぶなんて珍しいと思った。
〔2〕長髄彦との間で応戦した弓矢戦、そして神武天皇の弓の先に金鵄が止まり決着がついたこと。
〔3〕饒速日尊が宮を定めるために、矢を3本放ったこと。
〔4〕石切劔箭神社(大阪府東大阪市)の屋根に象徴されている「劔と箭」。
秀真文字の刻印された「矢」は皇統を示すものでもあり、極めて神聖なものだったのだ。
本郷川の向かいにある「かぎろひの丘」に500名〜1000名の兵を配置して、音羽山にむけて神武天皇お手製の和歌を歌ったのだろう。
何度か追い出そうとしたのだが出てくれないため、ティッシュペーパーで捕まえて出すことになった。
丸めたティッシュでハエを掴んだ瞬間、ハエは次のように言った。
「わが身をあなた様に捧げます」
と。
ハエの王はベルゼブブとして象徴されている。
「好きにさせておくように」
いつもの声だ。
ベルゼブブが戻れる時が近いのかもしれないが、まだ先のことだ。
神武天皇が初めて大和の地に立った場所が桜井市慈恩寺佐野である
| 桜井市慈恩寺佐野 |
奈良県桜井市慈恩寺佐野1 |
阿紀神社に宮を定めて、残党の一掃を図った。それが大室伝承。
| 生根神社 | 奈良県桜井市忍坂871 |
| 威徳神社(是室山?の南麓) | 奈良県宇陀市大宇陀区麻生田 |
この地で残党を一掃した後、女軍を配置して墨坂攻略の陣を張った。
女神が現れて、
「あなたさまをお慕い申し上げます」
そういう声だ。
| 皇大神社 | 奈良県宇陀市大宇陀区岩室第372番 |
「ここに来ないとかむやまといわれひこのみことにはなれないんだよ」
この言い方はいつもの声だ。
| 阿紀神社 | 奈良県宇陀市大宇陀区迫間252 |
お祭りの準備をしているおじいさんとおばあさんに音羽山が見えるかどうか聞いた。
実に詳しいおじいさんが出てこられた。
阿紀神社から音羽山は見えないが、本郷川を隔てたスグ向こうの「かぎろひの丘」に上がれば音羽山が見えること、西山岳の上を空山といい、空山から一段低くなったところを西山岳というのだそうだ。
「メメ坂」という地名も使っていたし、実に詳しい方だと思った。
八坂神社から音羽山が見えるかどうかも尋ねると、八坂神社からでは音羽山は近すぎて見えないという。
祝詞奏上後、レッドリバー犬を連れた女の子がやってきて、自分が作った小さい弓で矢を射て遊んでいる。
今の子が弓と矢を自分で作って遊ぶなんて珍しいと思った。

神武天皇にまつわって、弓で思い出す伝承は・・
〔1〕井光神社における天之羽羽矢伝承。〔2〕長髄彦との間で応戦した弓矢戦、そして神武天皇の弓の先に金鵄が止まり決着がついたこと。
〔3〕饒速日尊が宮を定めるために、矢を3本放ったこと。
〔4〕石切劔箭神社(大阪府東大阪市)の屋根に象徴されている「劔と箭」。
秀真文字の刻印された「矢」は皇統を示すものでもあり、極めて神聖なものだったのだ。
おそらく、阿紀神社の地が朝原祈祷地だと示したかったのかもしれない。
倭姫も、朝原祈祷地の言い伝えがあるからこそ、この地に立ち寄るのだ。本郷川の向かいにある「かぎろひの丘」に500名〜1000名の兵を配置して、音羽山にむけて神武天皇お手製の和歌を歌ったのだろう。
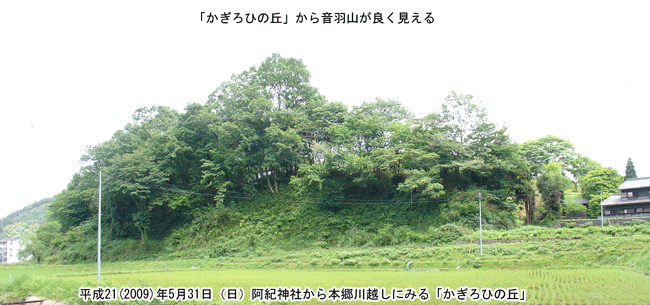
| 国見(くにみ)が丘に | 桜井市と宇陀市の境界をなす音羽山のこと。 | |
| 軍(いくさ)立て | 作る御歌(みうた)に | |
| 神風(かんかぜ)の | 伊勢(いせ)の海(うみ)なる | |
| 古(いにしえ)の | 八重(やえ)這(は)ひ求む | 古え、千暗の罪を免れ下民となって各地を放浪していた素盞鳴尊のこと。 |
| 細螺(しただみ)の | 吾子(あこ)よよ吾子(あこ)よ | 「細螺」とは、そろばん玉の形をした高さ2cmくらいの巻貝(食用)のこと。 |
| 細螺(しただみ)の | い這(は)ひ求めり | 細螺(しただみ)と「下民(したたみ)」を掛けている |
| 討(う)ちてし止(や)まん | ||
| この歌お | 諸(もろ)が歌(うた)えば | |
| 仇(あだ)が告(つ)ぐ | 暫(しばし)し考(かんが)ふ | |
| 饒速日命(にぎはやひ) | 「流浪男(さすらを)よす」と | 素盞鳴尊が流浪男(さすらを)になったことをさす。 |
| 雄叫(おたけ)びて | また一言(ひこと)がも | |
| 「天(あめ)から」と | 軍(いくさ)お退(ひ)けば | 神武天皇の軍勢が天意を受けた正当なものである、と認識するに至った。 |
| 味方(みかた)笑(ゑ)む |
| 音羽山 |
奈良県桜井市粟原 (阿紀神社の向かいにある「かぎろひの丘」にある万葉公園から撮影) |
| 八坂神社 | 奈良県宇陀市大宇陀区本郷 |
祝詞をあげていると、半袖の汚れた昔の作業服を着た人物(パソンの弟子の若者)が何かに怯えて震えている。
朝原祈祷地ではない場所をウソをいって朝原祈祷地と主張した人物だろうか?
| 丹生神社 | 奈良県宇陀市榛原区雨師(あまし)366 |
祝詞をあげていると、
「お前たちのやっていることがうまくいくと思っているのか」
と私を非難する声である。
この直前に行ってきた八坂神社で怯えていた人物とは全く様相が異なる。
この神社は丹生川上神社中社から勧請されたと伝わるので、丹生川上神社中社の本宮の位置に何かあるのかもしれない。
丹生川上神社中社の本宮の位置にはとても引っかかるモノを感じているので来月に訪ねてみることにした。
| 吉隠川(よなばりがわ) | 奈良県宇陀市榛原区柳 |
大和川の最上流である。
| 高龗神社(たかおかみ) | 奈良県宇陀市榛原区角柄408 |
高龗神社(たかおかみ)に行く前の声である。
「そなたたちがそこに行けば、子龍はまもなく止めるであろう。
子龍の成功を祈られよ」
「人は幸せになるためにこの世にやってきている。
子龍の幸せを祈られよ」
平成21(2009)年5月31日(日曜日)に帰京
平成21(2009)年5月30-31日(土曜日・日曜日)、次回へ
| 伊那佐山 | 奈良県宇陀市榛原区自明 |
| 惣社水分神社 | 奈良県宇陀郡菟田野町上芳野648 |
| 宇太水分神社(上社) |
奈良県宇陀市菟田野区古市場245 http://www1.odn.ne.jp/udanomikumari/ 第2殿に速秋津彦命が祀られている |
| 宇太水分神社(下社) | 奈良県宇陀市榛原区下井足635番地 |
| 鳥見山 | 奈良県宇陀市榛原区萩原 |
| 鳥見社(とみしゃ) | 奈良県宇陀市榛原区萩原 |
| メメ坂 | 奈良県宇陀郡大宇陀町迫間252 |
平成21(2009)年5月30日(土曜日)、朝原祈祷・・
|平成21(2009)年5月31日(日曜日)、宇陀という地域は・・・・|
Copyright (C) 2002-2014 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.
お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。