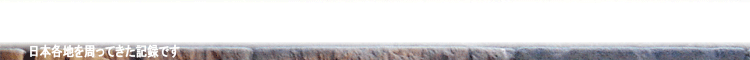私の物語の始まり(平成16年7月11日に収録)
そのきっかけになった出来事に焦点をあわせます。
7月28日(金曜日)夜、岩戸は人の心の奥底に秘められている
平成7(1995)年7月26日(水曜日)午後ことです。埼玉県朝霞市で飲食店を経営をされている中田さんという方が人づてで私たちの元を訪ねてきてくれました。
その方のお話というのは、日本のあそこに行ってくれ、こっちにいってくれという声が聞こえて日本各地を訪ね歩いている、というお話でした。
その場は、そういう人もいるのだなあ、と素直に感心して話を聞いていたのです。
しかし、中田さんたちが帰られてからが妙なのです、私の体に微妙な弱電を感じます。こういう場合、霊人がやってきているケースが多いということを平成7(1995)年6月に学ばさせていただいていたので、その方と話し合ってみることにしました。
平成7(1995)年7月28日(金曜日)夜、その方の話された事は次のような内容でした。
「私はアマテラスに会わなければいけない、私がアマテラスに会わなければ、天照は岩戸の中から出ることができないのだ、始めは戸隠にいるだろうと思っていたが、戸隠は地層がずれてしまっていて、以前のものではなくなってしまっていた、さあ大変、時間がないのだ、いろんなところに行ったが天照に会う算段がとれないのだ」私はその方に次のように告げました
「この度の岩戸は聖地にはないんだよ。人間の心の奥底に秘められていて、人間の心の奥底から入るしかないんだよ」その方は
「おお、かたじけない」といってその場を離れていきます。
8月3日(木曜日)午後、あの方はアマテラスに会えたのか・・
どうも落ち着かないのです。また何かきていそうなものを感じます。
「あの方にお会いされましたか」
と訊ねると、
「スサノオは私の気持ちをわかっていません、私がスサノオに会うのには条件があるのです、スサノオが黄泉国のことを調べて報告してくれるのでなければ会うことができないのです」「私が伝えてあげましょうか」
「それには及びません」
「あなたはこれからどこにおられますか?」
「あなたがたとともにいます」
断られた以上何もすることはできませんが、よくこういう霊的事柄好む人たちが私の周りに多いので、かくかくしかじかのことがあったんだと人の世の話題に乗せて数人に伝えたのでした。
9月5日(火曜日)、スサノオ黄泉国に降り立つ
こういう白日夢は見たことがある人でないとうまく伝わりきらないのですが、黄泉国の方では、その方が到着するのを今か今かとシビレを切らしながら待っていた雰囲気が伝わってきます。
黄泉国ではスサノオの到着点でスサノオを今や遅しと待っている人物がいます。
その人物に抱きかかえられて、スサノオは左手奥のほうに消えていきました。
黄泉大神(イザナミ尊)の元に連れて行ったのだろうと思います。
きっかけは、平成7(1995)年5月12日に父が亡くなってから・・
「ワシは、今から90年前に、90歳で長野の名もない農夫として亡くなっている、ソナタであればワシのところを突き止めて訊ねてくることもできようが、そんなことせんでよいぞ、ワシはそなたの教育のために遣わされてきた」
この爺さんとの話が実に楽しかった、自分の知りたいと思っている要点の全てを実にコンパクトに私にとっては衝撃的な言い方で教えてくれるのです。
ちなみに私の最初の質問
「なぜ、1年は12ヶ月で1週間は7日なのか」返答
「1年を12ヶ月にするのは神霊界の階層により、1週を7日にするのは喜びの数による」
この返答を聞いたとき私はとても感動しました、私の心奥にス〜っと沁みこんでいくのです、私はこの爺さん出来ると思いました、それからというもの、いろんなことを聞きました。
9年経った平成16年の今思い返しても本当に楽しかった、とても感謝しています。
6月23日(金曜日)、
「ワシからソナタへの教育はもう終わりじゃ」といって私の元を離れていくときに見せてくれた最後の映像、霊人から光と闇が分離し光は光の世界に、闇は闇の世界に入っていくという映像に神界にとって霊界がどのような位置にいるかをなんとなく感じ取ることができました。
そしてこれが最後の教育の教材なのだということも寂しさの中でなんとなくわかりました。
「ソナタの来るのをみんな待って居るぞ、あと解らないことは、神に聞け、そなたが訊ねれば、どのような神でも答えてくれるぞ」
これが平成7年 6月23日(金曜日)の、この爺さんの最後の言葉でした。
この後に、上に記録した天照大神・素盞鳴神のお話があったのです。平成7年8月12日(土曜日)午後、愛と希望の光の呼びかけ
10月7日(土曜日)までの2ヶ月間、極めてシンドイ日々だった。
平成7年11月26日(日曜日)、地の岩戸開き・千引の岩戸開き
千引の岩戸を開けるということは、伊邪那岐尊と伊邪那美尊の悲願に似た約束事でした。
そのことを、『ひふみ神示』は次のように書いています。「 ここに伊邪那美命息吹き給ひて千引岩を黄泉比良坂に引き塞へて、その石なかにして合ひ向ひ立たしてつつしみ申し給ひつらく、うつくしき吾が那勢命、時廻り来る時あれば、この千引の磐戸、共にあけなんと宣り給へり、ここに伊邪那岐命しかよけむ宣り給ひき。ここに妹伊邪那美命汝の国の人草日にちひと死と申し給ひき。伊邪那岐命宣り給はく、吾は千五百生まなむと申し給ひき。」
『ひふみ神示』(第6巻日月の巻、第40帖)より
山形県の出羽三山を擁する庄内地方で千引の岩戸開きが行われるとき、私たちはちょうど山形県羽黒町の実家に帰っていました。平成7年11月26日早朝ある神(稚姫岐美命のように思えているのだが)から千引の岩戸開きが行われるという知らせを受取ったとき、すかさず私だけ月山の方角に祈り羽黒山に向けて車を走らせました。このとき天の大神は次のようなお話をしてくれたと記憶しています。
「この岩戸は神のマコトの混じりのない気持ちでないと開けないこと、岩戸といわれるものは無限にあり、どの岩戸が千引の岩戸かどの神も分からない事、神の気持ちに呼応した岩戸が開けれること、ウソイツワリがあればウソイツワリの岩戸が開いてしまうこと、今時廻り来て大岩戸が開けられようとしている、ようく見ておかれよ」ホームページ「月の光」の由来は・・
あるいは、千引の岩戸開きは月山があるから庄内の地で行われたのかもしれません。私が生まれ育つなかで常に見てきた月山・羽黒山・湯殿山そして鳥海山、これらの山々を眺め見ることのできる庄内平野が「千引の岩戸開き」の足場となった土地でした。
千引の岩戸開きに立ち合わさせて頂いた直後に、私が4歳か5歳ごろよく「櫛」の映像を見ていたのを思い出しました。その櫛というは、伊邪那岐命の湯津々間櫛だったのだろうと思います。
上の『ひふみ神示』からの引用文の少し前にある一文
「伊邪那岐命、是見、畏みてとく帰り給へば、妹伊邪那美命はよもつしこめを追はしめき、ここに伊邪那岐命黒髪カツラ取り、また湯津々間櫛引きかけて、なげ棄て給ひき。」私だけの真実では、庄内にある湯殿山の「湯」は「湯津々間櫛」の「湯」です。
ご神体の赤茶の岩はお湯が湧き出ているから「湯殿」と名づけられたかのように考えられていますが、私だけの真実では、千引の岩戸閉めの際の湯津々間櫛を「湯殿」と尊称したものと考えられます。
私の実家がある羽黒町から湯殿山に車で行くには、櫛引町、朝日村と通っていきます。「櫛引」という地名は「湯津々間櫛引きかけて」の「櫛引」に因縁あっての地名のように思えます。羽黒、櫛引、朝日に「津々間(つつま)」なんていう地名があったら出来すぎだろうと思ってしまいますけれど。
千引の岩戸は無事開けられました。
時代が落ち着いて、私の物語が真実に沿っていそうなものなら、ぜひ羽黒山か月山か湯殿山で記念祭を執り行ってほしいところです。あるいは、羽黒山を開設された第32代崇峻天皇の子、蜂子皇子の因縁に基づいて奈良県の大和の地で記念祭を行うか、どちらかであってほしいと思います。19(絶対光)96年(くむとし)、平成8年(ひらくとし)来る
翌年の平成8(2006)年は主だった神々がそろう大事な年であるように思えます、さらに私たちにとっても子供が生まれるとても大事な年にあたっています。そういう大事な年がやってくることを私は次のように表現しました。
19(絶対光)96年(くむとし)、平成8年(ひらくとし)来る。
平成8年6月10日(月曜日)の神事(かみごと)とは・・
『ひふみ神示』第10巻 水の巻 第8帖 は次のように示しています。
「 鎮座は六月の十日であるぞ。」
昨年(平成7年の1995年)の未曾有の心霊現象や神霊現象を経験した私達にとって、平成8(2006)年6月10日は特別な日になっていました。何が鎮座するのかまでは、特定できませんでしたが、何かが鎮座されるのは確かです。
平成8(2006)年6月9日(日曜日)、夜10時に東京出発、翌6月10日(月曜日)奈良県吉野の天川神社に参拝、そこから和歌山県の高野山に入り、三重県菰野町の至恩郷に向かうという行程をくみました。ところが、これが難行程だったのです。
天川神社から高野山へつながる山間の道路の狭い幅員と険しさで時間だけが過ぎています。和歌山県の高野山を出発するのが6月10日の午後3時になっていましたから、6月10日の日のあるうちに三重県菰野町の至恩郷に辿り着けません。事情を説明すれば参拝できるかもしれないと思ったので、夜8時ごろ、本日中に参拝したい、夜11時ごろ伺えるけれどどうだろうという問合せの電話をしてみました。
電話口からは、日も暮れているので翌日にしたほうが良いのではないか、と当日中の参拝の断りの声が聞こえてきます。私たちだけに自覚された神事(かみごと)の成就という希望を明日につなぐため、夜11時過ぎに至恩郷の入り口の前に立ち、明日改めて訪ねてくる来るという心を置いてその場を立ち去ったのでした。
しかし、何がどういう風に鎮座されるのか、そして私達の果たす役割については皆目検討ついていませんでした。
翌日6月11日(火曜日)の早朝、三重県津市生まれである女房の両親の墓参り(三重県津市阿漕町津興〜マピオン地図〜の教円寺)を済ませてから伊勢神宮に車を向かわせました。
菩提樹の三重県津市阿漕町津興(マピオン地図)の教円寺から、伊勢神宮へ向けて車を走らせ始めると、妻がいいことをいいます。
「お父さん、鎮座するには足場が必要ということじゃない?」
近くにそれらしい名の神社を探すと、国魂神社(三重県津市西古河町23−16〜マピオン地図)という神社があります。ここは女房の実家に近い神社です。急きょ、国魂神社(三重県津市西古河町23−16〜マピオン地図)に立ち寄り祝詞を奏上しました。
祝詞を奏上している途中から、国魂神社から各地に伝令が発せられていきます。伝令は、
「国常立大神、鎮座まします、国常立大神、鎮座まします、・・・」といっていたのです。
6月11日(火曜日)、22時10分から夜の帳の中で、国常立大神に鎮座が開始されていきました。
「 鎮座は六月の十日であるぞ。」
ということで鎮座されるのは国常立大神であることを知ったわけです。国常立大神鎮座の規模の大きさは・・
2006年10月23日(月曜日)、旧暦9月2日、「新しい星が生れた」と知らされたのです。
その後、2008年2月28日(木曜日)、日経新聞で新惑星の理論的可能性が報じられました。平成8(1996)年6月11日(火曜日)の国常立大神鎮座という規模の大きさ、少なくとも太陽系を包括する規模だったのだろうと思います。
(※)この箇所は、平成20(2008)年6月頃に加筆しました。
猿田彦神社の摂社佐瑠女(さるめ)神社に鶴の御神紋・・
伊勢神宮では、子供を授かった感謝と昨年来のことを報告しました。
伊勢を出発し菰野町の至恩郷へ行く前に伊勢神宮の五十鈴川向かいにある、猿田彦神社にも立ち寄り参拝を済ませました。
そして、摂社の佐瑠女(さるめ)神社の前に来たとき、私は思わずしゃがみこんで賽銭受けに掲げてある御神紋をじっと見入ってしまいました。
というのも、猿田彦神社の摂社佐瑠女神社(さるめ)は丸に鶴の御神紋を掲げていたからです。

昨年来、鶴とか白鳥(しらとり)、あるいは観音の黄金輪は影となり日となり私たちを導いてきてくれていました。しかも私だけの真実では、鶴や観音は天御中主神に由縁を持ちます。いったい、どういう縁で天之宇受女が鶴の御神紋を掲げることが出来るのか?本当に疑問でしたし、驚きでした。
当時から8年経った平成16年の今ならなんとなく理解できる事柄なんですが、当時は本当に幼かったと思います。天之宇受女が鶴に縁ある神や事柄を尊敬したり慕ったりするのなら、鶴のご神紋を掲げたくなるのも道理であるというふうには考えだにしませんでした。
至恩郷にも鶴が・・
昨日今日のことを振り返りながら車を運転し、三重県三重軍菰野町大字菰野5833の至恩郷(マピオン地図)に到着したのは、平成8年6月11日(火曜日)の3時ごろでした。
昨夜の暗闇ではあたりの様子は分からなかったのですが、結構広々した様子です。
人影が見えないので、入り口からみて右手奥に見える小さな平屋のほうに声をかけました。奥から出てこられたのは、小柄な老女です。昨夜電話をしたのは私たちであること、伊勢神宮の参拝を済ませ、至恩郷の参拝に伺った旨を伝えると、まだ三貴神像を掲げている月の宮に案内してくれます。
(注)月の宮というのは・・
月の宮というのは、平成6年11月11日、千葉県成田市台方にある麻賀多神社から祭典に使用した廃材を頂戴し、それを材料に平成7年8月6日に落成した第二神殿のことです。ちなみに平成10年3月23日午前11時5分、ある方が至恩郷に訪ねて来られ敷地に足を踏み入れようとすると、敷地を掃除していたお手伝いの青年の箒の先から火が走り、日の宮、天明画室、道場が全焼してしまったそうです。しかし、この月の宮だけが消失から免れています。
(この注は平成16年5月私が記す)
月の宮への参拝を終え、今は消失している道場でお茶をご馳走になりながら岡本天明夫人である三典さんは小さな小箱を取り出して語り始めます、「平成5年8月6日、48回目の広島原爆投下日に爆心地に近い会場(エソール広島)で天明展を開催中、山形県酒田市の菅原さんご夫妻ら5人がご来場くださった。菅原さんご夫妻ら5人が昼食を取るために会場を出られ、平和公園近くの元安川橋のタモトを歩いていると、友人の足元に小さな折鶴が落ちていたそうです、菅原さんの奥さんはその鶴を拾ってもらい、折鶴を開けてみると、倉敷市玉島という文字の列が飛び込んできたそうです、そういう地名が印刷された新聞の折込広告の紙だったのです。菅原さんたち一行は今見てきた天明の生誕地をの名前を覚えておられましたから、直ちにその意味を解されて、私たちの元に届けてくれたのです」
そう言い、小さな小箱を開けて、中から取り出されたのは小さな折鶴だったのです。
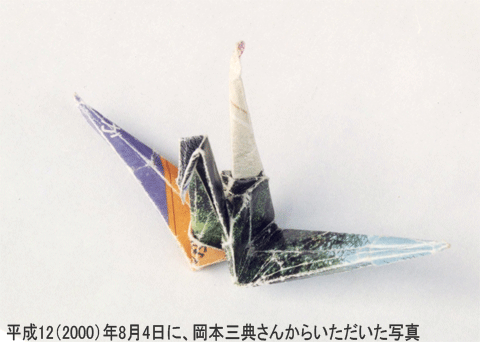
猿田彦神社の摂社佐瑠女(さるめ)神社で丸に鶴のご神紋を見て驚いた私です。
まるで天之宇受女が私たちに「私が天之宇受女でございます」
といって名刺を差し出してくれているかのように、その場の風景が、私にはこの世の現場と霊的現場の二重に見えていました。
鶴を手渡した菅原さんご一行は山形の酒田市だし、私は山形の酒田市に近い羽黒町で生まれ、鶴岡の鶴岡南高校で高校生活を送りました。酒田からでは月山が見えるかどうか微妙なところですが鳥海山ははっきりと見えるはずです。
三典さんのところで山形の庄内地方が交わっています。
三典夫人には三典夫人の鶴の物語がありますが、私は幼いころから私の鶴に対する物語を持っていました。そういう鶴の物語が至恩郷で交差したのです。
これ以来、私たち家族のあいだでは、三典夫人は「天之宇受女命」であるということになりました。
三典さんのお話を伺い、天明の生まれ故郷の氏神様である吉備津彦神社の資料を頂戴し東京に戻りました。
翻って、果たして本当に三典さんは天之宇受女命なのだろうか、三典さんが天之宇受女命だとすると天明は猿田彦命ということになるが、猿田彦命が太神の神示を受取る資格がどこにどういうふうにあるのだろうか、という具合に様々な疑問が頭を駆け巡ります。平成8年当時は、このあたりの事情は皆目見当がつきませんでした。8年経った平成16年の今なら、ある程度説明できます。下のメモ書きにあらすじを記載しておきます。
至恩郷を後にし車に乗り込むと黒住教の教祖・黒住宗忠が・・
すると、吉備津彦神社の資料と一緒にいたのかどうか分かりませんが、黒住教の教祖・黒住宗忠が私の眼前に現れて次のように言います
「天明の元を訪ねて、私の元を訪ねないでは、筋を違えるぞ。今回の出来事は全て私から始まったのである」
そういわれればそうともいえるので、東京に帰ってから黒住教の総本山のあるところを調べてみると、至恩郷の三典夫人から頂戴した吉備津彦神社から見て山の裏側にあたるところにあります。
急いで、吉備津彦神社、黒住教本山、吉備津神社(桃太郎伝説のある神社)、金光教本山、出雲へ参拝する旅程をくみました。
同じ6月という月の24日(月曜日)早朝に吉備津彦神社に到着する行程です。
吉備津神社(桃太郎伝説のある神社)に天之宇受女命を祀る一童社という摂社があり、ここでも天之宇受女命が念押しをされているようにも見えました。のちに本ホームページ「月の光」を2002年(平成14年)から編集に入り、その過程で猿田彦命は吉備の国で生まれ伊勢に渡っていったこと、天之宇受女命は吉備津神社の一童社において神上がられたことを神に教えていただいたのでした。
------------------------------------------------
平成18年4月15日の追記。
前頁に次のように書きました。 岡本天明 ⇒ 猿田彦命。猿田彦命の通常の根本使命は「人々を伊勢に向けさすお役」。
あるいは、野立彦命(『霊界物語』)である可能性の方が高い。
天の大神のお言葉を直接取り次げる位置にあるのは、野立彦命
本ホームページをなぜ「月の光」にしたか?
もう一つ大きな理由があるのですが、2011年(平成23年)ごろ記載してみたいと思います。 ←「私の物語」の先頭へ戻る
国常立大神鎮座の規模の大きさは・・
|新聞の折込広告|
幼いころから私の鶴に対する物語
Copyright (C) 2002-2014 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.
お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。