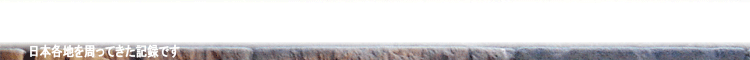平成24(2012)年7月28日(土)、旅行記録
平成24(2012)年7月28日(土)、旅行記録
第26代継体天皇が即位されてからの3つの宮
平成24(2012)年6月10日(日)の新宿(東京)でセミナーを開催。
東京セミナーで「伊邪那岐命と伊邪那美命の未完の国生み」について触れた。
この時、冊子を差し上げる予定でいたのだが、不安感に襲われて冊子の配布を止めることにした。
この不安感がどこからやってくるのかを突き詰めて考えてみると、第26代継体天皇の即位されてからの宮跡を訪ねていないからだと思えてきた。
「7月の終わりがいいよ」
という助言を得る。
その助言に従って、平成24(2012)年7月28-29日(土-日)に大阪セミナーを開催することにした。
この開会式に合わせて、第26代継体天皇の宮跡を訪ねてみることにした。 ← 日程表のトップに戻る
東京セミナーで「伊邪那岐命と伊邪那美命の未完の国生み」について触れた。
この時、冊子を差し上げる予定でいたのだが、不安感に襲われて冊子の配布を止めることにした。
この不安感がどこからやってくるのかを突き詰めて考えてみると、第26代継体天皇の即位されてからの宮跡を訪ねていないからだと思えてきた。
大阪セミナーを開催するときは、第26代継体天皇の宮跡を参拝する必要がありそうだ。
大阪セミナーの開催時期を考えていると、6月16日(土)に心の神様より「7月の終わりがいいよ」
という助言を得る。
その助言に従って、平成24(2012)年7月28-29日(土-日)に大阪セミナーを開催することにした。
平成24(2012)年7月28日(土)とは、第30回のロンドンオリンピックの開会式になっていた。
平成24(2012)年7月28日(土)5時(日本時間)から第30回のロンドンオリンピックが開催される。この開会式に合わせて、第26代継体天皇の宮跡を訪ねてみることにした。 ← 日程表のトップに戻る
 【4ヶ所】第26代継体天皇が即位されてからの3つの宮
【4ヶ所】第26代継体天皇が即位されてからの3つの宮
| 交野天神社の鳥居前の樟葉宮跡碑 | 大阪府枚方市楠葉丘2-19 |
2・3台の駐車スペースがあるという。
平成24(2012)年7月28日(土)の朝5時(日本時間)から、第30回ロンドンオリンピックの開幕セレモニーが行われている。その実況をラジオで聞きながら、6時15分に交野天神社に着いた。
鳥居や石碑の写真撮影をする。

| 交野天神社 | 大阪府枚方市楠葉丘2-19 |

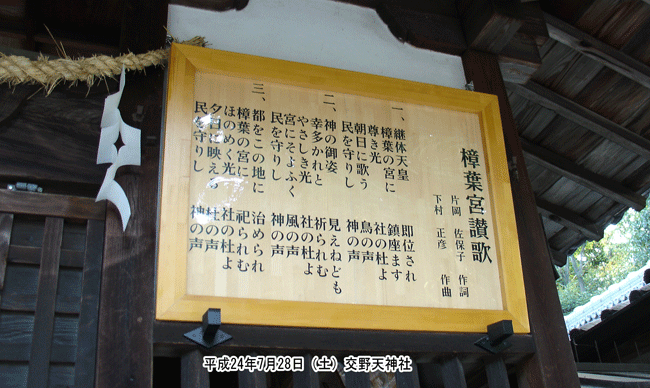
樟葉宮跡(現、貴船神社)への道を歩いていると天之大神から
「そなたたちがよく通った道じゃ」
というお言葉だった。
この時代は、女房と一緒にいたことを知った。
遠い昔の話だ。

| 樟葉宮跡の貴船神社 | 大阪府枚方市楠葉丘2-19 |
蚊の大群が私たちを出迎えてくれた。
痒いったらたまらない。
まだ第30回ロンドンオリンピックの開幕セレモニーが行われている。

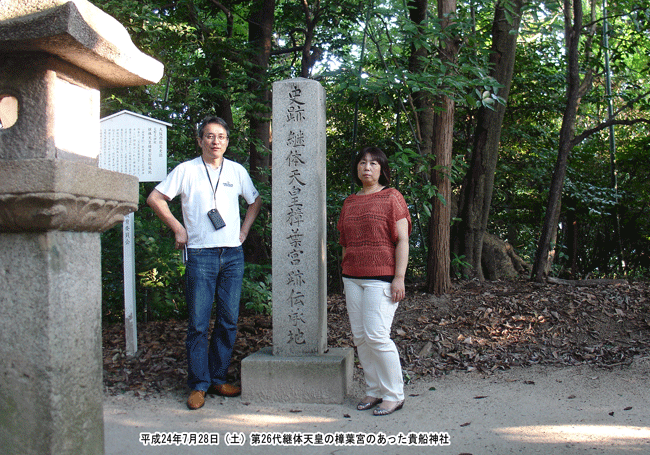
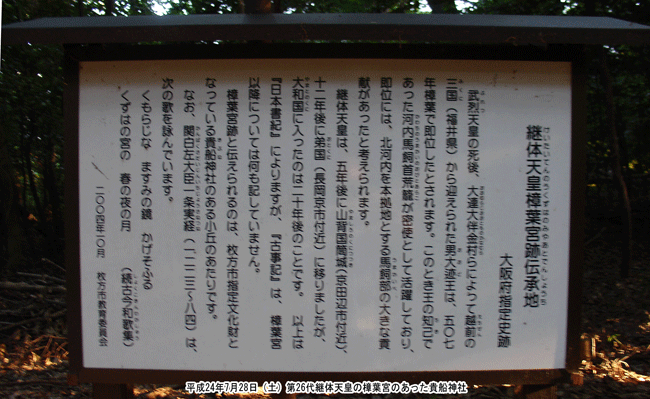
| 筒城宮(つつき) | 京都府京田辺市多々羅都谷1 |
同志社大学(京田辺市)の敷地内にある駐車場に車を留め、筒城宮(つつき)に向かった。
学生食堂らしい建物を左手にみて、歩いている方角の前に見える丘が筒城宮(つつき)の碑がある場所だ。
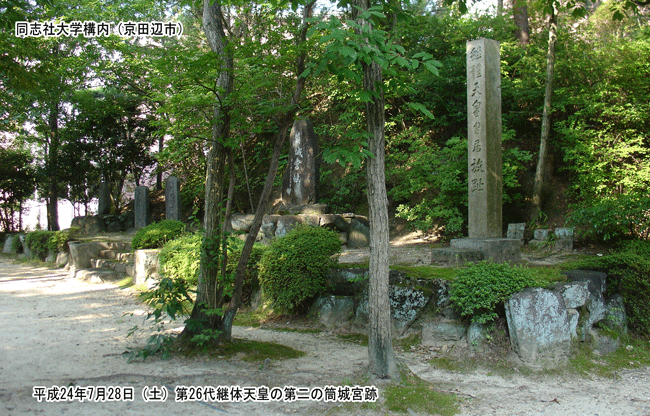
また、立札によると、第16代仁徳天皇皇后「磐之媛(いわのひめ)」も、この地に住んだという。
「磐之媛(いわのひめ)」は葛城山系の東麓、大和側に勢力を誇っていた葛城氏の娘で、四王子を生み、うち三人(第17代履中、第18代反正、第19代允恭)が天皇になった。
この地でも、第16代仁徳天皇の「嫉妬や妬みや恨み」に関係するような伝承がみられことは興味深い。
第26代継体天皇には、第16代仁徳天皇の影響が随所にあるようだ。
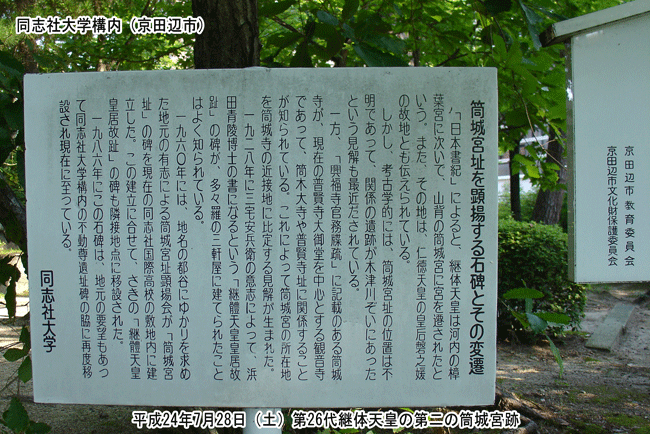
そういう思い出が蘇るとき、同志社大学(京田辺市)の敷地内に筒城宮(つつき)があることは実に興味深いことだ。
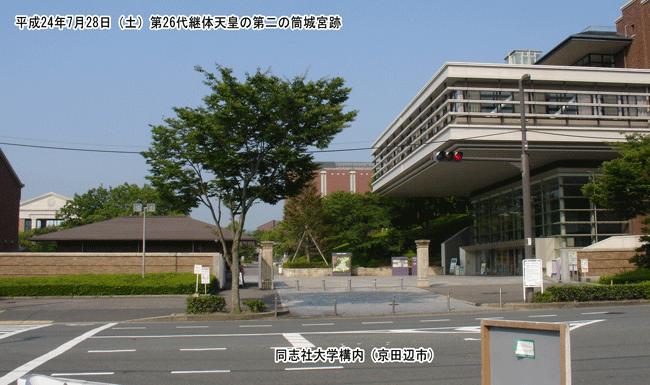
聖火が点される実況を聞きながら、次の弟国宮(おとくに)があったとされる乙訓寺に向かった。
| 弟国宮(おとくに)があったとされる乙訓寺 | 京都府長岡京市今里三丁目14−7 |
弟国宮(おとくに)があったとされる乙訓寺には、9時30分に到着した。
結局、弟国宮(おとくに)があったとされる乙訓寺には、開会式を開催中に到着できなかった。
ローソクの火に例えると、ローソクの火が消えた状態で、弟国宮(おとくに)があったとされる乙訓寺に着いたことになる。

この地帯が、八咫烏の孫に統治を託された土地柄であるという点が「キー」かも知れない。
奈良県の宇陀と同じような属性か、あるいは、奈良県の宇陀を映した土地であるか、というそういう問題だ。
○『日本書紀』の第11代垂仁天皇15年(紀元前14年)の条に、弟国の地名起源説話が載っている。
神武天皇の時から600年ほど経た物語だ。それによれば、丹波国の日葉酢媛(ひばすひめ)は皇后になって、2人の妹は妃になります。あとひとり4番目の妹竹野媛はその容姿が醜かったので出生地の丹波国に返された、といいます。
その途中、葛野(かどの)で自ら輿から落ちて死んでしまった。
そこで、その土地が堕国(おちくに)と呼ばれるようになったという。
○ 第11代垂仁天皇15年から500年ほど経た伝承だ。
寺名となっている乙訓(おとくに)は、今から1,500年前、葛野(かどの)郡から分離し新しい郡がつくられた際に、葛野(かどの)を「兄国(あにくに)」とし、新郡を「弟国(おとくに、乙訓)」としたことによるともいわれている。こうみると、500年から600年単位の伝承があることになる。
← 日程表のトップに戻る日程表のトップに戻る
Copyright (C) 2002-2014 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.
お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。